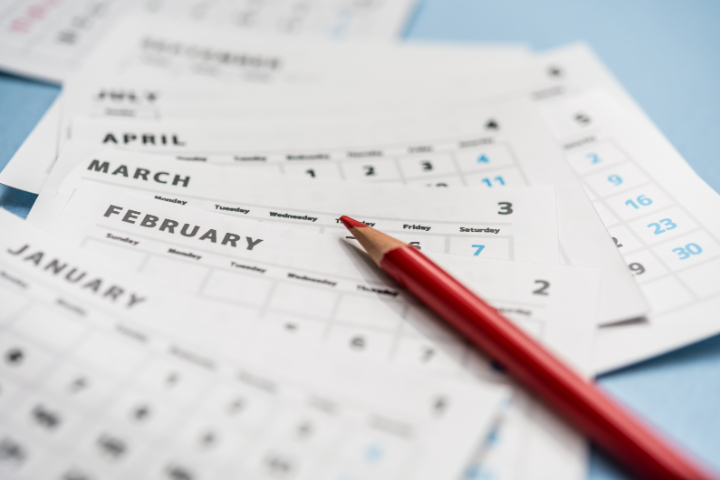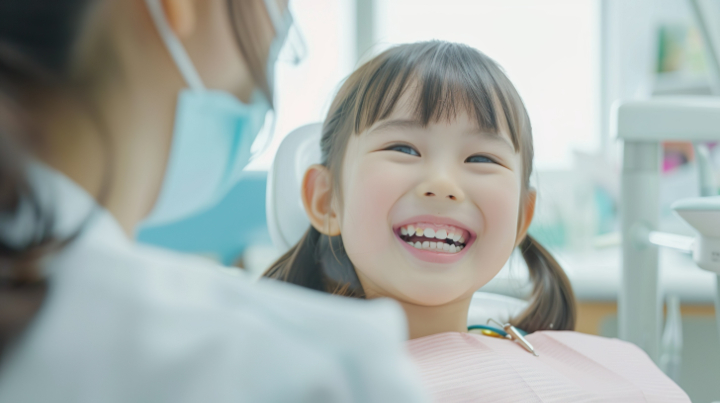プレオルソは後戻りする?原因・防ぎ方・対処法を詳しく解説

こんにちは。大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」です。
プレオルソは、子どもの歯並びや噛み合わせを整えるために用いられるマウスピース型の矯正装置です。痛みが少なく取り外し可能であることから、多くの保護者に選ばれている治療法ですが「治療後に後戻りしないか心配」という声も少なくありません。
実際に、使用状況や生活習慣によっては、矯正した歯並びが元に戻るリスクもあります。
この記事では、プレオルソによる後戻りの主な原因をはじめ、予防するための工夫や、万が一後戻りが起きた場合の対処法について詳しく解説します。
プレオルソとは

プレオルソとは、子どもの歯並びや噛み合わせを整えることを目的としたマウスピース型の矯正装置です。主に乳歯から永久歯に生え変わる6~12歳ごろの成長期に使用されます。
歯そのものを動かすのではなく、舌や口唇、顎の筋肉などのバランスを整えることで、正しい歯並びや噛み合わせへ導きます。装置は取り外しが可能で、日中の短時間や就寝中の装着が基本となるため、学校生活や日常生活への影響が少ない点も特徴です。
プレオルソは、歯並びだけでなく口呼吸や姿勢の改善にも効果が期待されており、総合的な口腔機能の育成を目指す矯正法として注目されています。
矯正治療後の後戻りとは

矯正治療後の後戻りとは、治療によって整えた歯並びが、時間の経過とともに元の位置に近づいていく現象を指します。歯は骨や歯ぐき、筋肉など周囲の組織と連動しており、それらの影響を受けてわずかに動く性質があります。
特に、矯正直後は歯を支える組織が安定していないため、適切な保定処置を行わなければ歯は元の位置に戻ろうとします。
後戻りは見た目だけでなく噛み合わせや口腔機能にも影響を与えることがあるため、矯正後の管理も治療の一環として重視されています。安定した結果を得るためには、定期的な通院と保定装置の継続使用が欠かせません。
プレオルソは後戻りしにくい?

プレオルソは、一般的なワイヤー矯正と比べて後戻りしにくいといわれています。その理由の一つに、歯並びだけでなく口周りの筋肉や舌の位置、呼吸方法といった口腔機能の改善を目的としている点が挙げられます。歯を無理に動かすのではなく、成長段階にある顎や筋肉のバランスを整えることで、自然な歯列の安定を促す仕組みです。そのため、矯正後も正しい機能が維持されれば、歯が元の位置に戻るリスクを抑えることができます。
ただし、装着時間や生活習慣によって結果は左右されるため、歯科医師の指導を守って治療を継続することが大切です。
プレオルソのメリット・デメリット

ここでは、プレオルソの代表的なメリットとデメリットについて、具体的に解説します。
プレオルソのメリット
プレオルソのメリットは、以下のとおりです。
口腔機能全体を整えられる
プレオルソは、舌の位置や口唇の筋肉、鼻呼吸など、歯並びに関係する周囲の機能を正しい状態へと導くことを重視しています。これにより、矯正終了後の安定性が高まり、後戻りのリスクも抑えられるとされています。
取り外しができて生活に支障が出にくい
プレオルソは就寝時を中心に装着する取り外し式の装置であるため、日中の学校生活や運動中の装着は不要です。食事や歯みがきの際にも取り外せるため、従来の固定式矯正に比べて生活への影響が少なく、衛生面でも優れています。
痛みや違和感が少ない
装置は柔らかい素材でできており、金属のような鋭利な部分がないため、装着時の痛みや口内炎などのトラブルが起こりにくい点もメリットです。矯正に対する心理的なハードルが低くなり、子どももスムーズに治療へ取り組みやすくなります。
治療費が抑えられる
プレオルソは費用が抑えられている場合が多く、経済的な負担を軽減できる点も多くの保護者から支持されています。初期費用が高額になりにくいため、矯正治療の導入として検討しやすい選択肢です。
プレオルソのデメリット
プレオルソのデメリットは、以下のとおりです。
装着時間が結果に影響する
プレオルソの効果は、装置の装着時間に大きく左右されます。装着時間が短い日が続くと、期待される効果が十分に得られないことがあります。使用状況の管理には、ご家族の協力が欠かせません。
適応できない症例がある
プレオルソは軽度〜中等度の歯列不正や噛み合わせのズレに対して効果的ですが、重度の骨格性の不正咬合や大きな歯列移動が必要な症例には適していません。そのような場合には、将来的にワイヤー矯正など他の方法への移行が必要になる可能性があります。
慣れるまでに違和感を覚えることがある
プレオルソは柔らかい素材で作られていますが、使用開始直後は異物感や発音のしづらさを感じることがあります。慣れるまでに時間がかかる場合もあり、特に、敏感なお子さんでは装着を嫌がることもあるため、根気よくサポートする姿勢が求められます。
自己管理が重要になる
装置の破損や紛失、装着忘れなどは治療効果に大きな影響を与えます。小さなお子さんの場合は、自らの意思でしっかりと管理するのが難しいこともあるため、保護者による日々の確認や声かけが必要です。
継続して使用するためには、ご家庭でのサポート体制が重要になります。
プレオルソで後戻りを防ぐには

ここでは、プレオルソで後戻りを防ぐ方法について解説していきます。
リテーナーの活用で歯の位置を安定させる
プレオルソによる治療が完了した後、多くの場合リテーナーと呼ばれる保定装置を使用します。歯並びが新しい位置にしっかりと定着するまで、動かないようにサポートするための装置です。
骨や歯ぐきが落ち着くまでの期間は、歯が再び動きやすい状態にあるため、リテーナーの装着が不可欠です。装着時間や使用期間については、歯科医師の指示に従い、適切に管理していくことが求められます。
正しい舌の位置や呼吸の習慣を継続する
プレオルソの特徴の一つに、舌や口唇などの筋肉の使い方を整える点が挙げられます。これは歯並びに直接関係する機能であり、正しい舌の位置や鼻呼吸ができていないと、矯正後に再び歯並びに悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、治療後も舌が上あごに正しく収まっているか、口がぽかんと開いていないかを日常的に確認することが大切です。口腔周囲の筋肉が正しい位置で働くことで、歯並びの安定性を高められます。
日常生活の習慣にも注意を向ける
歯並びは、食べ方や姿勢、寝るときの体勢など、日常生活のささいな習慣にも影響されます。例えば、頬杖をつく、指しゃぶりの癖が残っている、片側だけで食事をするといった行動は、無意識のうちに歯や顎に偏った力をかけてしまい、後戻りの原因となることがあります。
また、うつ伏せ寝や頬を押し付けるような寝姿勢も避けたほうがよいとされています。こうした習慣を意識的に見直し、歯に負担のかからない生活環境を整えることが、後戻りのリスクを下げるために欠かせません。
定期的な通院を続ける
治療後は、定期的に歯科医院で経過を確認してもらうことが大切です。歯の動きや口腔機能の状態を歯科医師がチェックし、必要に応じてアドバイスや追加の対応を行います。
後戻りが始まっている兆候が早期に見つかれば、簡単な処置で安定を取り戻すことも可能です。特に、成長期の子どもは体の変化が大きいため、治療後も一定期間は継続的なサポートを受けることが望ましいといえます。
プレオルソで後戻りをしてしまった場合の対処法

プレオルソによる矯正後に歯並びが後戻りした場合は、早期に適切な対処を行うことが大切です。後戻りが起きる背景には、リテーナーの装着が不十分であったり、舌の癖や口呼吸といった機能的な問題が再び現れたりすることがあります。
こうした場合、まずは歯科医師の診察を受け、後戻りの程度や原因を確認することが必要です。
軽度の後戻りであれば、再びプレオルソを装着して対応できる場合がありますが、既存の装置が合わない場合は、新たな装置が必要になります。舌のトレーニングや口腔筋機能療法を併用して、口腔内のバランスを整えることが重要です。
後戻りの兆候を放置すると、改善までに時間や費用が余分にかかる場合があります。違和感や見た目の変化に気づいた時点で、すぐに歯科医院を受診しましょう。
まとめ

プレオルソは、歯並びだけでなく舌や口唇の筋機能、呼吸習慣なども整えることで、後戻りが起こりにくいとされる矯正装置です。
しかし、装着時間の不足や生活習慣の乱れ、リテーナーの使用を怠ることで、治療後に歯が元の位置へ戻る可能性はゼロではありません。後戻りを防ぐためには、正しい装着習慣の継続、舌や呼吸のトレーニング、日常生活の見直し、定期的な歯科医師のフォローが欠かせません。
万が一後戻りが生じた場合でも、早期の対応で再び整った歯並びを目指すことが可能です。治療後のケアを丁寧に行うことで、プレオルソの効果を長く維持できるでしょう。
プレオルソを検討されている方は、大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、むし歯・歯周病治療や小児歯科、マウスピース矯正など、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、仮予約も受付しておりますので、ぜひご活用ください。