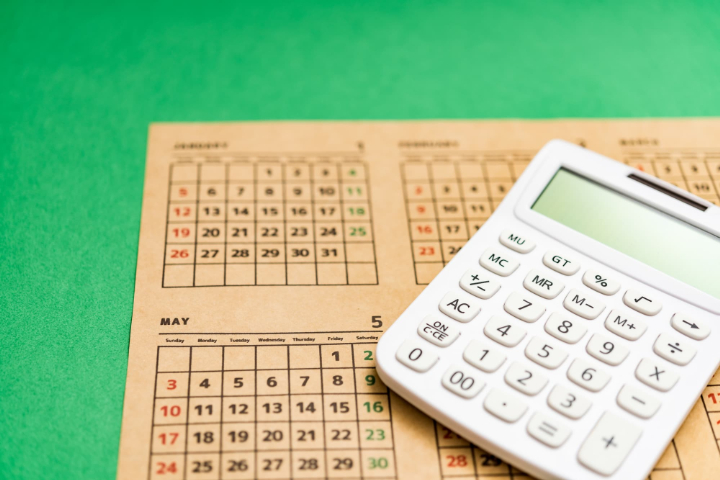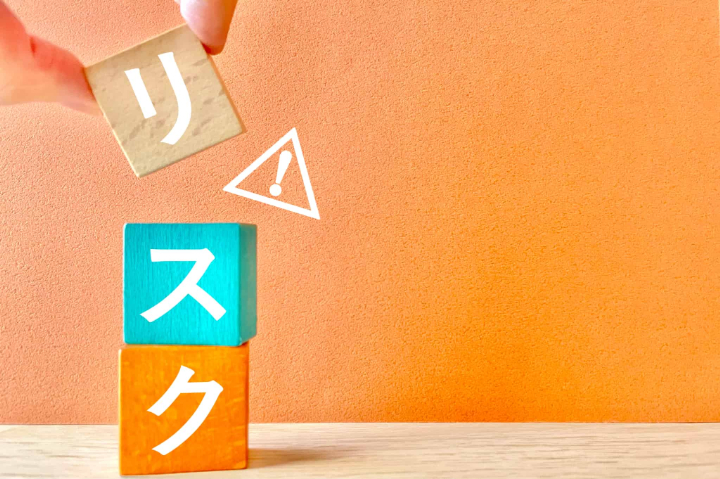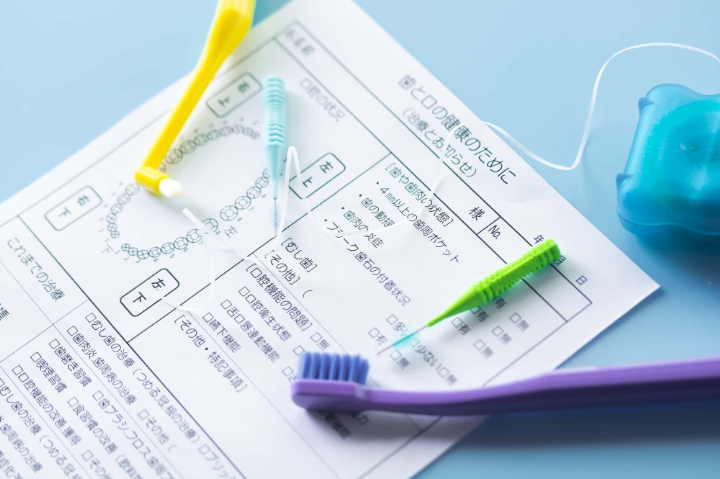インビザライン治療における抜歯の必要性と注意点を解説

こんにちは。大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」です。
インビザラインは、透明なマウスピースを用いて歯並びを整える矯正治療として人気を集めています。装置が目立ちにくく取り外し可能な点から、幅広い年代の方に選ばれている治療法です。
しかし「インビザラインでも抜歯が必要になるの?」という疑問を持つ方は少なくありません。歯を抜くと聞くと不安に感じる方も多いですが、実際には抜歯を伴うケースとそうでないケースがあり、患者さんの歯並びや顎の状態によって判断されます。
今回は、インビザライン治療において抜歯が必要なケースと不要なケースについて解説します。抜歯をするメリットやデメリット、費用についても解説しますので、インビザラインを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
インビザラインで抜歯が必要なケース

インビザラインで抜歯が必要なケースは、以下のとおりです。
歯を並べるスペースが不足している場合
歯が大きく、顎のスペースに余裕がないと、歯並びが重なってガタガタになってしまいます。インビザラインでは歯を適切に動かすためのスペースが必要となるため、重度の歯列不正では抜歯をしてスペースを確保することがあります。
出っ歯(上顎前突)の改善が必要な場合
上の前歯が前方に大きく突出している出っ歯は、非抜歯での改善が難しいケースが多いです。この場合、奥歯を後方へ移動させるだけでは限界があるため、前歯を後退させるスペースを作る目的で抜歯が行われます。
噛み合わせが深いケース(過蓋咬合)
上下の歯の重なりが深すぎる過蓋咬合では、スペース不足に加えて歯の動きに制限がかかることがあります。このような場合も、抜歯を行うことで歯の位置を調整しやすくなり、理想的な噛み合わせへ導きやすくなります。
顎と歯のバランスが極端に悪い場合
顎が小さいのに歯が大きいと、歯列全体が収まりきらずに前方や外側へ張り出してしまいます。このようなケースでは、抜歯をして歯と顎のバランスを整え、無理のない位置に歯を並べ直す必要があります。
インビザラインで抜歯が必要ないケース

インビザラインで抜歯が必要ないケースは、以下のとおりです。
軽度から中等度の歯列不正
歯並びの乱れが軽度〜中等度であれば、抜歯をせずに治療できることが多いです。例えば、前歯が少し重なっている程度や、隙間が目立つケースでは、インビザラインで歯を少しずつ移動させるだけで改善できるケースが多いです。
顎のスペースに余裕がある場合
顎の大きさと歯のサイズのバランスが取れている場合、抜歯をせずに歯を動かして整えることが可能です。歯を後方や側方へ移動させたり、歯の傾きを調整したりすることで、理想的な歯並びを実現できます。
ディスキング(IPR)で対応できる場合
ディスキング(IPR)とは、歯と歯の間を少しずつ削ってスペースを作る方法です。わずかなスペース不足であれば、抜歯を行わずにこの方法で歯を動かすスペースを作ることが可能です。歯を大きく削るわけではないため、歯の健康を保ちながら矯正治療を進められます。
奥歯を後方に移動できるケース
インビザラインでは、アタッチメントや顎間ゴムを活用して奥歯を後方へ移動させることができます。顎にある程度のスペースがあれば、この方法で抜歯をせずに歯並びを整えることも可能です。
インビザラインで抜歯をするメリット

ここでは、インビザラインで治療を進めるなかで抜歯をするメリットについて解説します。
十分なスペースを確保できる
抜歯を行うことで歯を動かすためのスペースが確保され、無理のない位置に歯を並べられるようになります。特に重度の歯列不正では、このスペースがあるかどうかが治療成功の大きなポイントとなります。
横顔のバランスが整いやすい
出っ歯や口元の突出感が強い場合、抜歯をして前歯を後方へ移動させることで、横顔の印象が大きく改善します。Eライン(鼻と顎を結んだ線)の内側に唇が収まりやすくなり、口元全体の美しさが増すメリットがあります。
安定した噛み合わせを得られる
抜歯をすることで歯と顎のバランスが整い、上下の歯がしっかり噛み合いやすくなります。見た目の改善だけでなく、咀嚼や発音の機能性も高まり、長期的に安定した口腔環境を維持できる可能性が高くなります。
治療後の後戻りを防ぎやすい
歯を無理に押し込んで整えた場合、治療後に元の位置に戻りやすくなることがあります。抜歯によって十分なスペースを確保することで、歯が安定しやすくなり、後戻りのリスクを軽減できるのも大きなメリットです。
インビザラインで抜歯をする場合の注意点

ここでは、インビザラインで抜歯をする場合の注意点について解説します。
治療期間が長くなる可能性がある
抜歯を伴う場合、スペースを閉じるための歯の移動に時間がかかります。そのため、非抜歯で行うケースよりも治療期間が長くなる傾向があります。特に大臼歯を動かす必要がある場合は、2年以上かかることもあります。
抜歯自体の負担がある
抜歯は外科処置であるため、術後に腫れや痛みが出ることがあります。また、心理的にも歯を抜くという行為に抵抗を感じる方は少なくありません。歯を失うことへの不安が大きなデメリットとして挙げられます。
顔立ちに影響を及ぼす可能性がある
抜歯をして歯列が後方に下がることで、口元が大きく変化する場合があります。バランスが良くなるケースが多い一方で、人によっては口元が下がりすぎて老けた印象を与える可能性もあるため、慎重な診断が必要です。
治療の難易度が上がる
抜歯を伴うインビザライン治療は、歯の移動量や噛み合わせの調整が複雑になるため、歯科医師の技術が重要になります。症例によってはインビザライン単独での治療が難しく、部分的にワイヤー矯正を併用するケースもあります。
インビザラインで抜歯をするタイミング

多くの場合、抜歯はインビザライン治療を始める前に行います。事前にスペースを確保しておくことで、マウスピースの設計がしやすくなり、治療計画通りに歯を動かすことができます。
症例によっては、インビザライン治療を進めている途中で抜歯が必要になることもあります。これは、想定よりも歯が動きにくい場合や、治療計画の修正が必要になった場合に行われます。
治療途中に抜歯をしたことで追加のアライナーが必要になると、費用がかかったり期間が延びたりすることがあります。
インビザラインで抜歯をする場合にかかる費用

矯正治療において抜歯をする場合は、保険は適用されません。抜歯をする場合にかかる費用は、1本あたり5,000円〜1万円程度です。外科的処置が必要になると費用が1万円を超えることもあります。抜歯の本数が増えると、その分費用もかかります。
まとめ

インビザラインは、装置が目立ちにくく、日常生活に支障をきたしにくい矯正方法として人気がありますが、歯並びの状態によっては抜歯が必要になる場合があります。
特に、重度の歯列不正や出っ歯、顎と歯のバランスが大きく崩れているケースでは、抜歯をしてスペースを確保することが治療成功の鍵となります。
一方で、軽度から中等度の歯並びであれば、ディスキングや奥歯の移動を活用することで抜歯をせずに治療できる可能性もあります。
抜歯を行うことで横顔のバランスや噛み合わせが改善しやすくなりますが、治療期間の延長や抜歯そのものの負担といったデメリットも存在します。抜歯をするタイミングや本数は個々の症例によって異なり、歯科医師による精密な診断が不可欠です。
インビザラインで抜歯が必要かどうかは自己判断できるものではなく、歯科医師による精密検査とカウンセリングを通じて最適な治療方針を決定することが大切です。
正しい知識を持ち、メリット・デメリットを理解したうえで治療に臨むことで、理想的な歯並びと美しい口元を実現できるでしょう。
インビザラインを検討されている方は、大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、むし歯・歯周病治療や小児歯科、マウスピース矯正など、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、仮予約も受付しておりますので、ぜひご活用ください。